見ざる言わざる聞かざるとは?意味や英語は?
見ざる言わざる聞かざるの意味①人の生き方を示す教訓

見ざる言わざる聞かざるの意味の1つ目は、人の生き方を示す教訓となることです。ことわざとしても存在している言葉ですね。意味としては、人の欠点やあやまち、自分にとって損となることなどを、見たり、聞いたり、おこなったりしない方が良いというものになります。人間がやってしまいがちな行動を戒めたものです。
見ざる言わざる聞かざるという教訓やことわざは、自分にとって都合の悪いものを受け入れないことや、保身のために余計なことに関心をもたないほうが良いという意味で誤用されることもあります。ネガティブな意味ではなく、ポジティブな意味合いで使われるものなので、注意するようにしましょう。
この他にも、教訓となることわざなどを探してみたい方は、こちらの記事が便利です。人気のものや有名なものを、豊富にそろえているので、自分にぴったりだと思えるものを探してみてはいかがでしょうか。

見ざる言わざる聞かざるの意味②「ざる」は打ち消しを表す古語

見ざる言わざる聞かざるの意味の2つ目は、「ざる」という表現は、古語の打ち消しの表現が連体形となったものだということです。つまり、「見ざる=見ない」という意味になりますね。「ざる」という音が、「猿」に似ていることから、「見猿・聞か猿・言わ猿」という文字が当てられることもあります。
見ざる言わざる聞かざるの意味③日光東照宮の彫刻を表す

見ざる言わざる聞かざるの意味の3つ目は、日光東照宮の彫刻を表すものだということです。神厩舎という神馬をつなぐための馬屋に彫られたもので、耳を塞いだ猿、口を塞いだ猿、目を塞いだ猿という、ユーモラスな様子が表されています。重要文化財にも指定されている、とても有名な彫刻ですね。
こちらの三猿が、見ざる言わざる聞かざるの像の代表格として、扱われる傾向にあります。ちなみに、三猿がいる神厩舎の彫刻は一つだけではありません。じつは、全八面からなる大作だったりします。子猿たちが母猿に育てられることから始まり、独り立ちして家族を持つまでを描いているとされています。
三猿の彫刻は二面目の、猿の幼少期を彫り込んだものです。目、耳、口を塞いで、幼いうちは悪いものに触れず、良いものを受け入れるよう教えられている場面となります。猿の生涯を人の生涯にたとえて、生き方の教訓を説いたものとなっています。
見ざる言わざる聞かざるの英語①悪を見ない・聞かない・話さない

見ざる言わざる聞かざるの英語の1つ目は、「悪を見ない・聞かない・話さない」という意味のものです。英語では、「See no evil, hear no evil, speak no evil」いう形で存在しています。
英語でも、日本語とまったく同じ意味の教訓として使われているものですね。異なる点といえば、聞くことと言うことの順序が、英語と日本語では逆だということぐらいです。
見ざる言わざる聞かざるの英語②賢い三匹の猿

見ざる言わざる聞かざるの英語の2つ目は、「賢い三匹の猿」という意味の「Three wise monkeys」ですね。日光東照宮の三猿のように、目、耳、口を塞いだ、三匹の猿の意匠そのものを表す言葉です。意匠そのものに、悪いもの見ない・聞かない・話さないという教えが込められていると考えられています。
見ざる言わざる聞かざるの由来は?
見ざる言わざる聞かざるの由来①論語の一節が由来

見ざる言わざる聞かざるの由来の1つ目は、論語の一節が由来となることです。儒教の開祖である孔子が記した論語の中に、礼節について触れた一節があります。簡単にまとめると、礼節に背くことに注目せず、聴くことをせず、話さず、行わないよう戒めているものです。「見る・聞く・言う・行う」の4つの戒めとなりますね。
見ざる言わざる聞かざるの由来は、孔子の教えをより分かりやすく伝えるために、猿を用いて表現するようになったからだと言われています。孔子が生きた時代は紀元前552年から479年のことなので、約2500年も前に、由来となる概念が誕生していたことになります。
孔子の論語の表現について、さらに詳しく知りたい方は、こちらの記事などに目を通してみましょう。「不惑」という言葉の意味をまとめるとともに、おすすめの論語の書籍も紹介しています。はるか昔から、大切に守られてきた教えに詳しくなるチャンスです。

見ざる言わざる聞かざるの由来②天台宗の教えで日本に伝播

見ざる言わざる聞かざるの由来の2つ目は、日本に伝搬したのは、天台宗の教えが由来となったためだということです。孔子の教えが形を変えたものが、8世紀ごろに日本に伝わり、天台宗の教えとして定着したとされています。
天台宗の教えの内容は、孔子のものとは若干異なり、「自らの心を惑わすようなものは、見ない・聞かない・話さない」という解釈になったと伝えられています。孔子の時代から1000年以上過ぎているため、教えが広まると同時に、さまざまな解釈がされるようになったと考えられています。
由来を見てみると、見ざる言わざる聞かざるの概念が日本に定着したのは、かなり古い時代だったことが分かります。長い時間を経て、ことわざとしても定着してきたんですね。
見ざる言わざる聞かざるの由来③庚申信仰とともに三猿が伝播
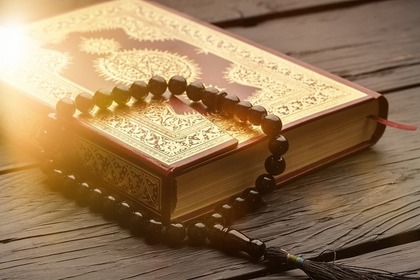
見ざる言わざる聞かざるの由来の3つ目は、庚申信仰とともに、三猿のモチーフが日本に伝播したということです。庚申信仰とは、十干十二支の庚申(かのえさる)の組み合わせのことで、庚申の日に行われる行事信仰のことを指します。
もとは中国の道教からくる信仰で、庚申の日に眠ると、人間の体内にいる三戸虫が天帝のもとへと抜け出し、その人の罪悪を告げ口すると考えられているものです。さらに、信仰の対象となるのが庚申(かのえさる)の日であることから、やがて猿を神様の使いとして考えるようになりました。
その結果、三戸虫の告げ口を封じるために、「悪事を見ない・聞かない・話さない」という、三猿のモチーフが誕生したと言われています。現在知られているモチーフの由来には、庚申の三戸虫と猿の結びつきがあったというわけですね。
本当は四猿だった?見ざる言わざる聞かざるの三猿になった理由は?
四猿から三猿になった理由①四という数字が悪かったため

四猿から三猿になった理由の1つ目は、四という数字が悪かったためというものです。由来となった孔子の教えによると、もとは「見る・聞く・言う・行う」の4つの行為を戒めるものでした。つまり、「見ざる・言わざる・聞かざる・行わざる」の、四猿であることがオリジナルだったわけです。
しかし、現代に伝えられているものは、三猿しかありませんね。理由は、四猿の持つ、「四」という数字にあるとされています。「四(し)」は、「死(し)」に通じるため、縁起の悪い数字として捉えられますね。死を連想させるため、四は省かれて、三猿だけになったのだという説です。
四猿から三猿になった理由②公にできる意味ではなかったため

四猿から三猿になった理由の2つ目は、四猿目が公にできる意味ではなかったためだというものです。孔子の教えをもとにした、四猿の像が存在しますが、そのモチーフを見てみると詳しいことが分かります。目、耳、口を塞いでいる点は共通しているのですが、四匹目となる、最後の猿が塞いでいるものは、自分の股間です。
つまり、「見ざる・言わざる・聞かざる・行わざる」の「行わざる」は、性的な意味合いを含んでいたのだと解釈できます。悪い意味ではないのですが、公にするには、少しためらわれる内容ですね。性的な表現を控えようとする意識が、四猿を三猿だけにしたのだという説があります。
四猿から三猿になった理由③語呂がよくなかったため

四猿から三猿になった理由の3つ目は、語呂がよくなかったためだというものです。単純に日本語として口に出すと、4つの語から成る表現は、言いやすいものではありませんね。リズムもとりにくいので、なんとなく省きたくなってしまいます。
また、3つの語で構成されるほうがキリは良くなりますし、語呂が良いほうが、人の頭にも残りやすいというメリットもありますね。口に出したときのリズムの良さを考慮して、四猿から三猿だけになったのだという説があります。
見ざる言わざる聞かざるがある場所は?
見ざる言わざる聞かざるがある場所①栃木県の日光市

見ざる言わざる聞かざるがある場所の1つ目は、栃木県の日光市です。三猿の像の中でも、とくに知名度が高いのが、栃木県の日光市にある日光東照宮の欄間の彫刻となっています。明治時代に海外に紹介されたことから、有名になったもので、世界的に見ても三猿の像の代表格となっています。
江戸時代の初期に、左甚五郎という彫刻職人によって彫られたものですが、幾度にもわたる修復を経て現代に残ったものです。最後の修復は2017年に行われたものなので、キレイに色が塗り直された姿を、楽しむことができます。
見ざる言わざる聞かざるがある場所②京都府の京都市

見ざる言わざる聞かざるがある場所の2つ目は、京都市の京都市にある、大黒山金剛寺となります。八坂庚申堂(やさかこうしんどう)とも呼ばれることから分かるように、庚申信仰と関係があるお寺です。三猿のモチーフの由来となった信仰ですね。
大黒山金剛寺の三猿の像は、三門の上に設置されています。瓦の上なので、多少距離をおかないと見えづらいかもしれません。こちらは彫刻ではないので、瓦の質感に似た三匹の猿が、耳、口、目を可愛らしく塞いでいる姿をとっているものです。
京都には、大黒山金剛寺だけではなく、訪問してみたい歴史ある寺社がたくさんありますね。おすすめスポットを巡り歩くためには、旅館やホテルをおさえておくことも大切です。人気の場所をチェックしてみたい方は、こちらの記事も併せてご覧ください。ランキングや朝食などのおすすめポイントが分かりますよ。

見ざる言わざる聞かざるがある場所③インドのアフマダーバード

見ざる言わざる聞かざるがある場所の3つ目は、インドのアフマダーバードです。三猿の像は、日本特有のものだと思われがちですが、そうではありません。孔子の教えが広まったためか、三猿の像は世界各地に存在します。
アフマダーバードは、インド西部にある、グジャラート州の主要都市ですが、こちらにある三猿の像も有名です。グジャラート州は、あの有名なマハトマ・ガンディーの出身地でもあることが関係します。
マハトマ・ガンディーの逸話のなかに、常に三猿の像を身につけていたというものがあるためですね。「悪を見るな・聞くな・言うな」という教えを伝えるためだったと言われています。インドの教科書にも取り扱われているものなので、インド人にとっても馴染み深いものだと考えられます。
見ざる言わざる聞かざるのバリエーションは?
バリエーション①見ざる言わざる聞かざる思わざる

バリエーションの1つ目は、滋賀県の日吉神社に関係する、「見ざる言わざる聞かざる思わざる」というものです。973年に、比叡山延暦寺18代目座主である良源が、日吉神社に、「ざる」が用いられた処世訓を奉じたことが由来だと言われています。
良源の処世訓の中に、「見ず聞かず、言わざるの3つの猿よりも、思わざることこそ大事である」のようの記された一節があります。生きていくうえで、恨みや怒りなど、他人に対しての悪い心を持たないことが最も大切だという意味が込められているものです。
バリエーション②よく見・よく聞いて・よく話そう

バリエーションの2つ目は、埼玉県の秩父神社にある、彫刻が表すものです。秩父神社にも、日光東照宮と同じように、三猿の彫刻が施されている場所があります。しかし、こちらの彫刻は、見開いた大きな目と、おしゃべりをする猿の姿が印象的です。
日光の彫刻とは対照的に、「よく見・よく聞いて・よく話そう」という意味になったものですね。情報化社会にふさわしい意味の猿だということで有名になっています。対極の意味のバリエーションとなった、珍しいケースですね。親しみを込めて、「お元気三猿」と呼ばれています。
見ざる言わざる聞かざるで賢く生きよう
日光の彫刻で有名な見ざる言わざる聞かざるですが、人生にとって大事な教訓となる意味が含まれていることが分かりましたね。日本国内だけでなく、世界中で知られているものなので、万国共通の説得力があることが窺えます。教訓を大切にして、賢く生きていく方法を実践していきましょう。
商品やサービスを紹介する記事の内容は、必ずしもそれらの効能・効果を保証するものではございません。
商品やサービスのご購入・ご利用に関して、当メディア運営者は一切の責任を負いません。
KEYWORD
関連のキーワード
NEW
新着記事
RANKING
人気の記事













